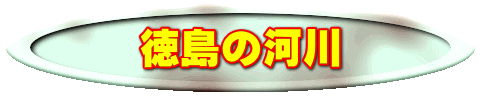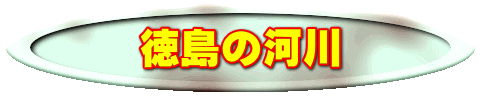鐘の由来
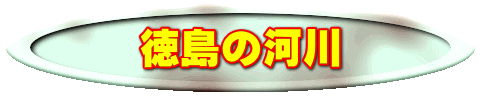
トップページ>高知県の観光>徳島の河川>鮎喰川>鐘の由来
焼山寺
本寺の鐘は松平阿波守忠英朝臣(蜂須賀二代目藩主)大檀主となられ、慶安二年(1649年)二月二十三日寄進されたものである。当時蜂須賀公は二つの鐘を造り、一つを本寺に、いま一つを徳島市内の某寺に寄進されたそうである。本寺の鐘は撞けば殷々たる響きは徳島市内にまで届いたという。あと一つの市内のものは少しも良い音を出さず、公は人を使わして本寺の鐘と替えたいと申されたという。然し鐘は「いなーん いなーん」と鳴って、それは果たされなかったという。昭和十六年大東亞戦争に供出の命下り青年多数によって山麓まで運ばれ、其処より馬車に積んだが、馬俄かに腹痛を訴え、もだえ苦しんだ、馬子は遂に鐘を運ぶことを断念して他の器物を運んだ。かくして戦争は終わり、県文化財として指定を受け、別の場所に保存し、今は二代目の鐘が響いている。