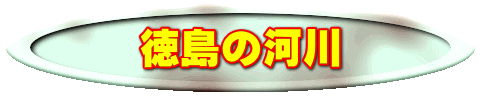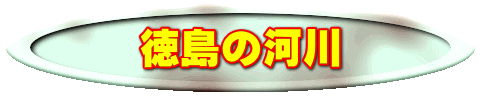一宮城跡
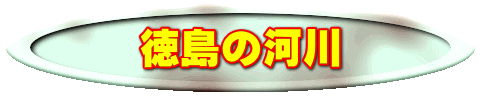
トップページ>高知県の観光>徳島の河川>鮎喰川>一宮城跡
県指定史跡
一宮城は暦応元(1338)年、小笠原(一宮)長宗による築城とされ、鮎食川の清流を前に臨み、背後には重畳たる山岳を控える県内最大級の山城跡である。一宮氏の山城として整備されたが、天正十(1582)年、長宗我部元親の侵攻を受け、また、天正十三(1585)年、豊臣秀吉の四国征伐時には、鮎食川を挟んだ辰ヶ山に陣を構えたとされる豊臣秀吉と長宗我部元親との攻防の舞台となった。同年、豊臣秀吉の命により阿波に封ぜられた蜂須賀家政は一宮城を居城としたが、翌年、徳島城に移ると徳島城の支城(阿波九城の一つ)として、家臣の益田長行に守城させた。元和元(1615)年の徳川幕府の一国一城令によって、寛永十五(1638)年癈城となった。現在、標高144mの山頂の本丸を取り巻くように、明神丸・才蔵丸・小倉丸・権ノ丸・水ノ手丸などの曲輪、堀や土塁が遺存し南北朝時代から戦国時代にかけての山城の荒々しさと、それを守っていた当時の武士の剛健な気風をしのばせる。現地点から約600mで本丸跡に至る。また、山麓の寄神社周辺は「御殿居」と呼ばれ、城主の居館跡であるとの伝承が残っている。
(看板引用)