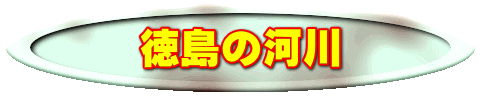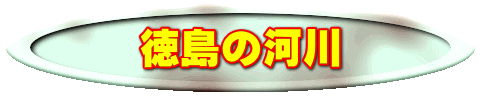一宮城本丸跡
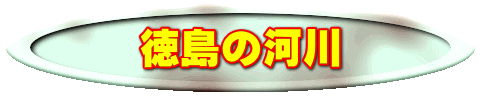
トップページ>高知県の観光>徳島の河川>鮎喰川>一宮城本丸跡
一宮城跡
一宮城は、前方に鮎喰川、後方に険しい山々がそびえ立つ自然の要塞に築かれた大規模な山城であった。現在では、標高144メートルの本丸跡に石塁が残っており、その他、明神丸・才蔵丸・水手丸・小倉丸・椎丸・倉庫跡の遺構も明らかで、貯水池といわれるくぼ地もその跡をとどめている。この城は、南北朝時代、南朝に味方していた山岳武士の拠点であり、一宮氏が長年居城としていたが、成祐のとき土佐の長宗我部氏に占拠された。その後、豊臣秀吉が四国を平定し、天正13年(1585)、蜂須賀氏が最初入城したのが、一宮城であった。翌年、蜂須賀氏が徳島城に移ってからは、その支城として有力家臣を置いて守らせたが、元和元年(1615)の一国一城令により、廃城となった。なお、一宮城跡は県指定史跡となっている。また、一宮城跡周辺には、本殿が国の重要文化財に指定されている一宮神社、四国88ヶ所第13番札所の大日寺などの観光名所がある。
(看板引用)